こんにちは、こえじまです。
共働き夫婦のみなさま、生活費をどちらがいくら負担するか悩んでいませんか?
我が家では夫婦の家計を考える時に色々パターン分けしてどれが合うか両者が納得するまで話し合いました。
本記事ではその中で出てきた生活費分担パターンを3つと考える時の4つのポイントをご紹介します。
生活費分担パターン3つ
個別生活費口座
生活費分担パターンの1つ目は支出のカテゴリ(費目)ごとに支払う担当者を決める個別生活費口座パターンです。
例えば、
- 家賃と光熱費は旦那で負担
- 食費や日用品費は奥様側で負担
というような分け方です。
それぞれが自分の担当分だけ把握しておけば良いので、毎月夫婦で話し合って収支を管理しなくてもなんとかなることが大きなメリットです。
悪く言うとパートナー分の収支が見えず、どんぶり勘定となりやすいので、相手にいくらお小遣いがあるのかが見えなかったり、あればあるだけ使ってしまうようなタイプだと貯まりにくいといったデメリットがあります。
また、子供が出来た等で食費や日用品費の支払いが増えた、イレギュラーな出費が出た、などの際に適宜柔軟に費用分担を見直さないと不満が出やすいという点もあります。
共同生活費口座(定額拠出)
毎月収支を把握する必要があり管理は少し煩雑になりますが、個人的には共同生活費口座パターンがオススメです。
お金の流れを把握するための4種類の口座について以下記事で解説しています。よければこちらもどうぞ!
生活費専用の共同口座を作ることで、夫婦どちらかが働けなくなった(旦那がケガをした、奥様が妊娠出産で一時的に収入が減った等)時でも、費用分担を変えるだけでどうにかなります。
個別生活費口座で家賃が旦那の口座から引き落とされているケースだと、仮に旦那が一時的にケガで働けなくなると、家賃支払用の口座にお金がちゃんとあるようにイレギュラーな振込をしないといけなかったり、漏れがあると引き落としが出来ず慌てたりします。
夫婦の出費は共同口座から引き落とす、と決めてしまえばそれ専用のクレジットカードも作りやすいですし、お金の流れが分かりやすくなります。
共同生活費口座(定額拠出)パターンでは、夫婦それぞれが共同口座に対して毎月決まった額を入金します。
手取り収入の大小に応じて共同口座に旦那20万、奥様15万、のような感じで毎月振り込むイメージです。
給与額が安定しているのであればこのパターンがわかりやすいのでオススメです。
共同生活費口座(パーセント拠出)
一方こちらは同じく共同生活費口座ですが、共同口座への入金額を手取りに対する比率(パーセント)で管理するパターンです。
月ごとに給与が変動するような仕事をしている場合は毎月の給料の◯パーセントを共同口座に入金する、とすると管理しやすくなります。
下振れてしまったときに支払いが足りなくなってないか毎月確認する必要があることがデメリットです。
共同生活費口座(パーセント拠出)は、夫婦間でそれぞれの収入金額が分かるようになるので、家庭の経済状況が見える化され、一番貯まりやすいです。
夫婦の生活費負担を考える時の4つのポイント
夫婦間の収入額がどれくらい違うか
まず考えるポイントとしては夫婦間でどれくらい収入に差があるかです。
例えば旦那は月の手取りが50万だけれど、奥様は月の手取りが10万、みたいなケースですね。(ちなみに我が家は結婚当初、奥様の方が年収が高かったです。)
収入額が同じくらいであれば負担割合も同じくらい、ということで分かりやすいですが、差があるのであればその違い分をどこかで合わせないと不満が出ます。
先ほどの50万、10万のケースで言うと、仮に夫婦両方の生活費負担を10万円ずつにした場合、奥様側には1円も残らず、当然ながら不満が溜まります。
こんな極端なケースは少ないと思いますが、負担割合が夫婦にとって妥当かどうかをきちんと話し合って決めましょう。
- 生活費負担額をパーセントで決めると、収入が低い方のお小遣いが少なくなりすぎる
- いや、稼いでるんだからその分お小遣いも多くないとおかしい!パーセントで決めるべき!
- それは分かったが、パーセントで決めてしまうと少なくなりすぎるので最低限の額は欲しい!
- じゃあ基本はパーセントで決めるけど、お小遣いとして最低限は残るように調整しよう
などの議論が我が家ではありました。
給料の変動があるか?(給料が定額か?)
2つ目は給料が変動性かどうかです。
- 残業があるか無いかで手取り給与が大きく変わる
- 成果給なので毎月変動が激しい
- 個人事業主なので収入が安定しない
などですね。
このような場合、毎月必ず引き落とされる家賃や光熱費などの担当となるのはオススメ出来ません。
毎月給与が支払い分を満たせるかどうかを確認し、足りなければパートナーから振り込んでもらうなど無駄な振込手数料や手間が増えてしまうからです。
このようなパターンだと共同生活費口座にしておくのが良いでしょう。
パートナーに内緒にしたい財布が欲しいか?
続いては夫婦間の収入の透明性についてです。
家計は出来るだけ見える化したほうが貯まりやすいのは事実です。(支出が見えることで無駄なものが見え、節約しやすくなる)
ですが、パートナーに自分の飲み代を知られたくないなど、様々な事情があるかもしれません。
その場合は、支払い種別ごとに担当を決める個別生活費口座か共同生活費口座(定額拠出)にするのがオススメです。
毎月の支払いさえ出来ていれば相手にとやかく言われる筋合いはありません。
ちなみに我が家は給与明細をそのまま夫婦間で共有しており、完全にオープンです。
ボーナスや臨時収入はあてにしない
生活費負担を考える際に、基本的にボーナスや臨時収入はあてにしないようにしましょう。
毎月の支払いは毎月の収入でまかなうことが基本です。ボーナスは会社の業績や個人の成果によって変動がありますし、0円のケースもあります。
月給が少なくおさえられており、ボーナスで多めにもらえるような企業にお勤めのケースは要検討ですが、そうでない場合はボーナスや臨時収入は全て臨時出費や、貯金・投資に回すようにしましょう。
我が家の例
我が家では共同生活費口座(パーセント拠出)を採用しました。
夫婦それぞれの収入に対して、以下の比率で割り振っていました。
| カテゴリ | 給与 | 賞与 |
|---|---|---|
| 生活費 | 35% | |
| 貯金/投資 | 35% | 80% |
| 個人(お小遣い) | 30% | 20% |
何を生活費、何をお小遣いとするかの境界を明確にして、それぞれに合った比率を考えてみましょう。
現在は貯金/投資を増やそうと夫婦で頑張っているので、お小遣いをそれぞれが不満を持たない最低額に減らしています。(定額拠出)
また、毎月NISAの積立枠があるので、お小遣いと合わせて天引きしたうえで生活費と貯金/投資をパーセントで計算しています。
| カテゴリ | 給与 | 賞与 |
|---|---|---|
| 生活費 | 個人とNISAを引いた額の65% | |
| 貯金/投資 | 個人とNISAを引いた額の35% | 80% |
| NISA(積立枠) | ◯万円 | |
| 個人(お小遣い) | ◯万円 | 20% |
貯金/投資と書いていますが、生活防衛資金は既に貯まっているので最近の貯金/投資枠は全て投資に回っています。
生活防衛資金やお金についての知識はリベ大の本が非常にオススメです。辞書のように太い本ですが、トピックごとに解説されていて数ページで完結しますし、イラストも多いのでとても読みやすいですよ。
まとめ
本記事ではその中で出てきた生活費分担パターンを3つと考える時の4つのポイントをご紹介しました。
各家庭にあった生活費管理方法を見つけ、ストレスなくお金の管理をしましょう!
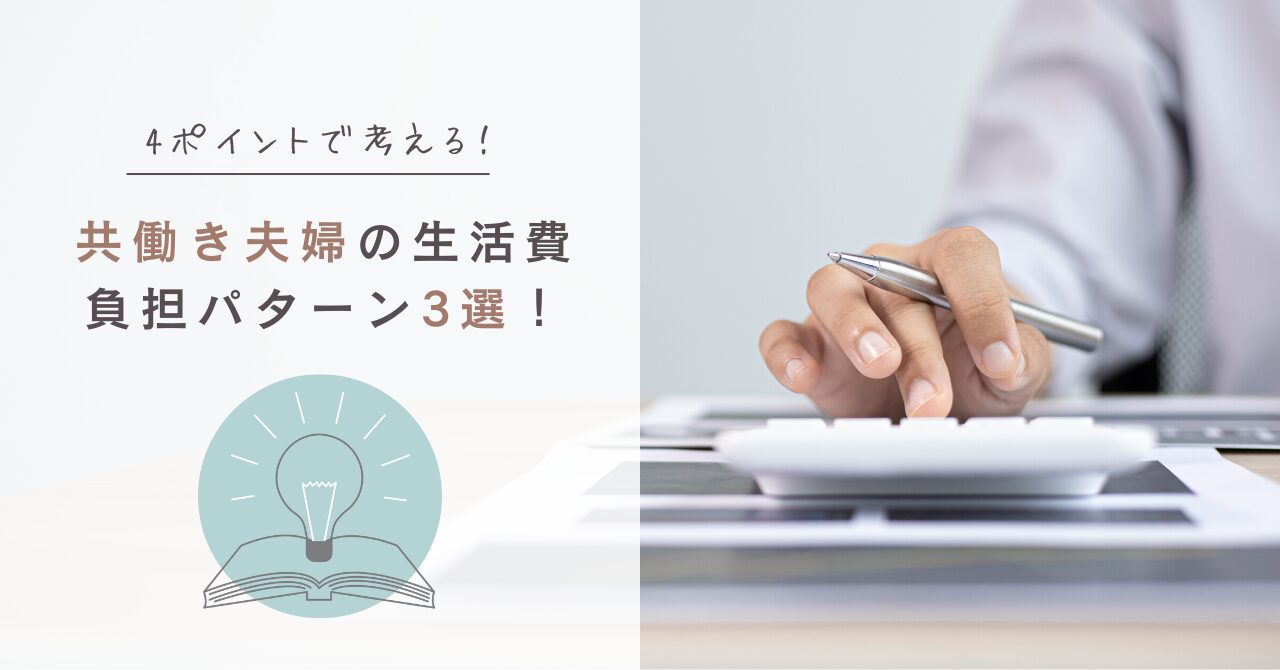


![改訂版 本当の自由を手に入れる お金の大学 [ 両@リベ大学長 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3780/9784023323780_1_3.jpg?_ex=128x128)


コメント