こんにちは、こえじまです。
赤ちゃんの夜泣き、辛いですよね。赤ちゃんは泣くのが仕事だと言われても、それでも夜起こされるのは辛いです。
我が家ではどうにも私が耐えきれず、第一子の時は生後3ヶ月、第二子の時は生後2ヶ月の時からネントレ(ねんねトレーニング)を始めました。
たった2週間で夜ぐっすりと寝てくれるようになり、かなり肉体的にも精神的にも楽になりましたよ!
本記事ではネントレの具体的なやり方と、さらにぐっすりと寝てくれるための方法3つをご紹介します。
夜に泣き声で起こされるのが本当に辛かった
ネントレを知ったのは第一子が生後3ヶ月くらいになった頃でした。1ヶ月の育休を取り、仕事に復帰して2ヶ月ほど経った頃です。
当時(今でもそうですが)夫婦子供同じ寝室で、広い部屋では無かったので、赤ちゃんが泣くと部屋に反響して地獄でした。
一度寝たらめったに起きない私ですら起きるほどの泣き声で、毎晩起こされるのがとてもとても苦痛でした。
夜泣きのだいたいの原因は「お腹すいた」だったので、以下のようなミルクケースに粉ミルクを寝る前にセットしておいて量る手間を減らしたり、湯冷ましを準備してすぐに作れるように工夫はしていました。
我が家でミルク作りの時短に使っていたおすすめアイテムはこちらの記事で紹介しています。良ければこちらもどうぞ!
それでも睡眠が妨げられるのが辛いものは辛い!そんな時に見つけたのがネントレでした。
ネントレとはねんねトレーニングのことで、これをやると夜ぐっすり寝てくれるとのこと。寝るのにトレーニングが必要なのか!と目からウロコが落ちた私は本を数冊読み、実践してみました。
当時読んだ本としては以下の3冊でしたが、おすすめは2冊目の「赤ちゃん寝かしつけの新常識」です。
第一子はそれから2〜3週間ほどで夜ぐっすり寝てくれるようになり、生後4ヶ月になる頃には夜起きない日の方が多くなってきました。
第二子は生後2ヶ月でネントレを始め、生後2ヶ月半くらいで既に週に3〜6回は夜10時から朝7時まで9時間ぶっ通しで寝ていました。
ネントレの具体的なやり方
基本的にはベッドに寝かせて放置するだけ
ネントレとは「赤ちゃんが自分の力で寝れるようにトレーニングする」ということです。
とは言っても特別なトレーニングは必要ありません。
暗い部屋にベッドを移し、赤ちゃんが自分の力で寝れるように待つだけです。
ポイントは一定の時間、赤ちゃんがギャン泣きしようが喚こうがなんだろうが別室(か赤ちゃんから見えないところ)で待つことです。
最初は1分から始めましょう。1分過ぎたら赤ちゃんの様子を見に行き、「ねんねだよ〜」と声をかけたり、トントンしたりしてまた去ります。また1分過ぎたら様子を見に行く、というのを繰り返します。
数日ごとに様子を見に行く間隔を2分→3分→5分と徐々に伸ばしていきましょう。
ギャン泣きしても耐える
個人差はありますが、生後2ヶ月くらいになると夜通し寝れる体力が実はあります。
ネントレの初期はギャン泣きが止まらないと思いますが、ここが耐え時です。
心配になって何度も見に行ってしまっては赤ちゃんの寝る力が育ちません。
始めは泣き声で胃が痛くなるかもしれませんが、(私はなっていました)我が子に成長の機会を与えているんだと考えて耐えましょう。
ストップウォッチで計ったり、今日は何回目で寝るかな…?と回数を数えることで少しは気が楽になりますよ。
注意点
寝かせる前や一定時間経った後に寝る環境がきちんと整っているか確認しておきましょう。
ミルクを飲みたてでゲップが溜まっていないか、おむつは濡れていないか、暑い、寒いは無いかは特に確認しておきましょう。
大人だって気持ち悪かったり、部屋が暑すぎたら寝にくいはずです。環境はしっかりと整えてあげましょう。
また、寝返りができるようになると気付くとうつ伏せで寝ている場合があります。生後2ヶ月から6ヶ月くらいは乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスクが高いので、必ずあお向けになるようひっくり返しましょう。
平成28年におこなわれた消費者庁の発表によると、0歳児における不慮の事故死のなかでは、「窒息によるもの」の割合が高く、特に就寝時の窒息死事故が多数起きているということです。なかでも顔がマットレスなどに埋まる事例が最も多いということでした。
【医師監修】赤ちゃんをうつぶせ寝させるときの注意点(メリット・デメリット) – https://baby-calendar.jp/knowledge/baby/1142
ひっくり返すとまたギャン泣きされたりもするのですが、窒息するよりはマシです。そこは心を鬼にしましょう。
ネントレと一緒にやると良いこと
生活リズムを整える
まずは生活リズムを整えることです。
大人でも日中帯ずっと寝続けてたら夜寝れなくなりますよね。赤ちゃんも同じで、日中帯寝すぎると夜眠れなくなります。
生後1ヶ月くらいになると段々とリズムを整えることが出来るようになってくるので、寝る時間を調整しましょう。目安としては、以下の表くらいです。
| 月齢 | 夜の睡眠時間 | 昼の睡眠時間 | 合計睡眠時間 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9時間 | 6時間 | 15時間 |
| 3ヶ月 | 10時間 | 3.5時間 | 13.5時間 |
| 6ヶ月 | 10.5時間 | 2.5時間 | 13時間 |
| 9ヶ月 | 11時間 | 2時間 | 13時間 |
| 12ヶ月 | 11時間 | 1.5時間 | 12.5時間 |
| 18ヶ月(1.5歳) | 11.5時間 | 1時間 | 12.5時間 |
| 24ヶ月(2歳) | 11時間 | 1時間 | 12時間 |
個人差があるので必ず上の表通りじゃないといけないということはありません。目安として参考にしてみてください。
我が家では第一子、第二子ともにだいたい上の表通りにリズムを整えて夜ぐっすり寝てくれるようになりました。
経験上、昼寝の時間が長くなりすぎる傾向にあるので、昼の睡眠時間を越えそうであれば濡れたおしぼりを当てたり扇風機で寒い風を当てたりして起こしていました。
ひどいと言われるかもしれませんが、夜ぐっすり寝てもらうためにこちらも必死です。笑
予防接種後や病気、体調不良の時は睡眠時間を削らずたっぷり寝かせてあげるようにしましょう。良く寝て良く食べないと治るものも治りません。
睡眠時間の管理にはぴよログが便利です。こちらの記事でご紹介しているので良ければこちらもどうぞ!
抱っこしたまま寝かさない
できる限り抱っこしたまま寝かせないようにしましょう。
自分の力で寝れるようになるために、ベッドや布団の上で寝る習慣を付けましょう。
昼の寝かしつけは抱っこしても良いですが、寝付いたらベッドに下ろすようにしましょう。下ろした時に背中がベッドに当たると起きてしまう(俗に言う背中スイッチ)ので抱っこしたまま、というのもわかるのですが、それだと寝るトレーニングになりません。
背中スイッチ対策にはトッポンチーノを使うのがオススメです。
昼と夜の寝る環境を変える(特に夜はホワイトノイズをかける)
最後は昼と夜の寝る環境を変えるということです。
明確に環境を分けることで「今は寝る時間なんだ」と赤ちゃんが理解しやすくなります。
我が家では、以下のように使い分けていました。
| 時間 | 環境 |
|---|---|
| 昼 | ・適度な騒がしさ(あえて静かにしたりしない) ・普段着のまま ・真っ暗にはせず、適度に明るい状態 |
| 夜 | ・ホワイトノイズをかけて寝ることに集中させる ・寝る時用のスリーパーを着せる ・部屋は真っ暗 |
特に夜のホワイトノイズは効果抜群です。(テレビの砂嵐みたいなザーって音です)
これがあると無いとでは寝付くまでの時間がかなり変わります。
家にいる時はサーキュレーターを回し、サーキュレーターのブーンという音をホワイトノイズとしてつかっています。旅行先ではiPhoneのバックグラウンドミュージック機能でホワイトノイズをかけています。
まとめ
本記事ではネントレの具体的なやり方と、さらにぐっすりと寝てくれるための方法3つをご紹介しました。
夜ぐっすり寝てくれるようになると、精神的にも体力的にもかなり楽になります。ぜひ早いうちから始めましょう!
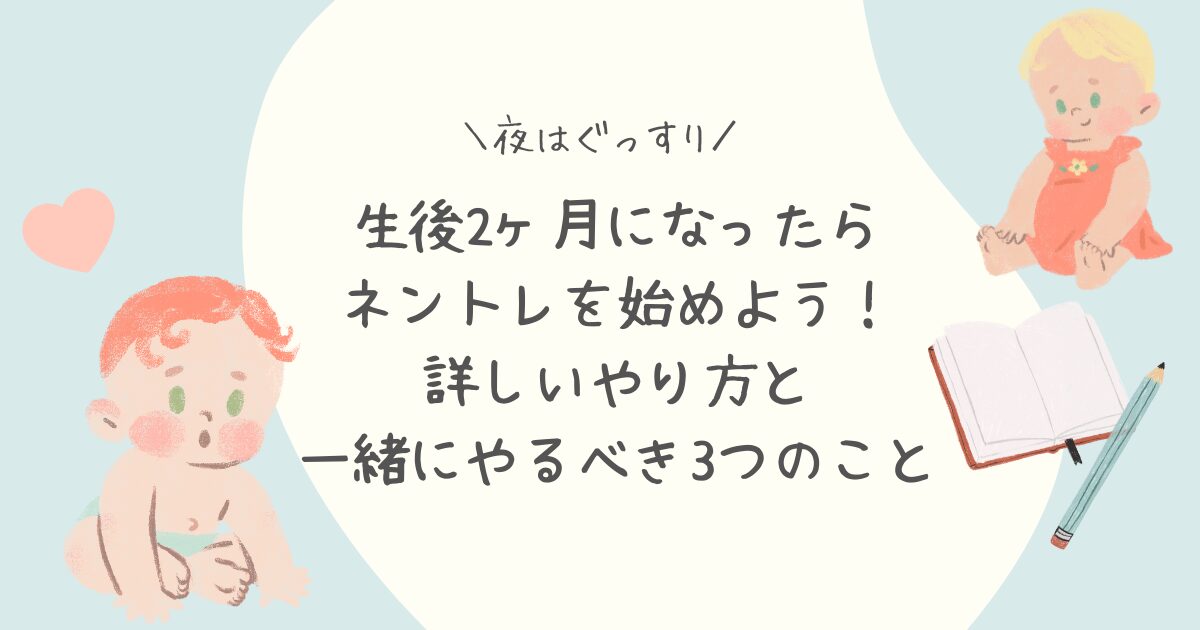

![【ラッピング対象】【KEYUCA公式店】ケユカ 抗菌離乳食&ミルクケース [日本製 国産 粉ミルク 持ち歩き 持ち運び 連結 シンプル 電子レンジ対応 食洗器対応 通販]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/keyuca/cabinet/35/3301261.jpg?_ex=128x128)
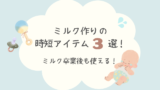
![家族そろってぐっすり眠れる 医者が教える赤ちゃん快眠メソッド [ 星野 恭子 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6846/9784478106846.jpg?_ex=128x128)
![赤ちゃん寝かしつけの新常識 赤いライトで朝までぐっすり [ ソフィア アクセルロッド ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2985/9784491042985.jpg?_ex=128x128)
![赤ちゃんとおかあさんの快眠講座 改訂版 ジーナ式 カリスマ・ナニーが教える [ ジーナ・フォード ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6336/9784022516336.jpg?_ex=128x128)


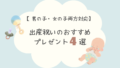

コメント